| |
| 頭文字つの登場人物 |
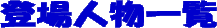 |
戦国本の登場人物の紹介 |
上総介の読んだ戦国本に登場する人物を紹介。主人公や脇役の紹介はこちら。
|
|
|
常陸・鹿島郡塚原の領主、塚原土佐守、塚原卜伝の養父、
|
|
|
|
|
唐津藩主・寺澤氏に滅ぼされた松浦党の一族、幡随院長兵衛の父、主君の仇を討つため放浪中に下関で病死
|
|
|
|
|
北条家の家臣、北条滅亡後浪人し津軽家に仕えた、津軽為信の三女を娶り津軽姓を名乗る、大光寺城主、為信没後の後継争いで津軽熊千代の擁立を図るが敗れ追放された
|
|
|
|
|
津軽為信の長男、宮内大輔、キリシタンに帰依し洗礼を受けた、父に先立って死去
|
|
|
|
|
津軽為信の三男、弘前城主、父の死後に兄の子・津軽熊千代と家督を争って勝ち家督相続、弘前城を築城した、徳川家康の養女を妻にする
|
|
|
|
|
富樫家重臣、槻橋豊前守一族、本願寺弾圧の中心人物、政親・幸千代の家督相続争いでは政親に味方した、北加賀半国守護代、長亨一揆で一揆方に討ち取られた
|
|
|
|
|
富樫家重臣、加賀月橋村に住む重代の被官、流亡の富樫成春を迎える、政親と幸千代の家督相続争いでは政親に味方した
|
|
|
|
|
津久見美作守の子、大友義鎮の側近、大友二階崩れで父・美作が義鎮の父・義鑑の殺害に加担したため自刃した
|
|
|
|
|
大友義鎮の重臣、大友二階崩れの変の当事者、義鑑から義鎮廃嫡と塩市丸の家督相続に反対し殺されそうになる、田口蔵人と共に大友館に侵入して義鑑に重傷を負わせたがその場で討たれた
|
|
|
|
|
加藤嘉明の家臣、関ケ原では留守居役、このとき西軍の毛利・河野連合軍による伊予侵攻を奇襲により撃退、その後松前城下で一揆を起こした河野家の遺臣を鎮圧した
|
|
|
|
|
福島正則の家臣、大阪の陣ののちに明石掃部の次男・内記を匿った、そのことを密告するものがあり、江戸の福島藩邸で拷問にあっても口を割らなかったため処刑された
|
|
|
|
|
柘植宗家の次男、三之丞清広、本能寺の変後の家康の伊賀越え、一族を率いて信楽から伊勢白子への道を誘導した、しかし加太越えに及んで対立関係にあった鹿伏兎一族の支配地なので暇を賜り、米地九左衛門政次に託した、関ヶ原の戦いに参戦し甲賀郡三百石を領す、大坂冬の陣にも参戦した
|
|
|
|
|
伊賀の土豪・福地伊予守宗隆の子といわれる、伊勢国主・北畠具教に仕えた、織田信長の伊勢侵攻に鬼瘤口の大将として出陣、具教が織田家と和睦後は北畠(織田)信雄に仕え家老の筆頭格となった、伊賀征伐に出陣したが討死した、ちなみに俳聖・松尾芭蕉は柘植一族の出といわれる
|
|
|
|
|
秀吉の黄母衣衆、備中守、通称・与左衛門、娘は福島正則の正室、福島家が安芸・備後に転封後八千石となった
|
|
|
|
|
織田信長の家臣、中川重政の弟、四郎左衛門尉、隼人正、津田盛月、兄と柴田勝家が揉めた際に勝家の家臣を斬って逐電、のちに羽柴秀吉に仕え小牧長久手の戦いに従軍、その後は主に秀吉に服従しない武将への使者として活躍、徳川家康の上洛を実現させ、北条氏や奥羽の武将への使者にもなった
|
|
|
|
|
福島正則の家臣、津田四郎兵衛、妻は来島長親の娘、江戸家老をつとめる、福島家改易後は信州に同行し正則の死を看取った、そのとき幕府からの検死役が来る前に正則を荼毘にふした、後に改めて福島正利に三千石を給して旗本となった
|
|
|
|
|
備前岡山藩主・池田忠雄の家老、一人娘が渡辺数馬の妻、数馬が仇討ちのため退身するとともに藩を退身し、在所の備前・牛窓に引きこもった
|
|
|
|
|
明智光秀の家臣、津田信春といわれるが定かでない、山崎の合戦では本隊右翼を受け持った
|
|
|
|
|
駿河今川家の海賊奉行、岡部忠兵衛貞綱、今川家が落ち目になったときに、向井将監にくどかれ武田水軍として仕えた、金丸筑前守虎義の子・金丸惣蔵の目覚しい働きに一目ぼれして養子にもらい、信玄の命で土屋に改姓した、長篠の合戦で討死した
|
|
|
|
|
大久保長安の兄、父大蔵大夫金春七郎喜然の嫡男、大蔵新之丞、武田信玄の小姓となった、土屋昌次の寄子となって土屋姓をもらい土屋新之丞と称した、長篠の戦いにおいて土屋昌次とともに討死した
|
|
|
|
|
武田家の重臣・金丸筑前守虎義の二男、土屋昌恒の兄、信玄の奥近習、金丸平八郎、甲州の名族土屋氏の名跡を継ぎ土屋姓を名乗った、信玄没後に殉死を願い出たが高坂弾正忠昌信に止められた、長篠の戦いで討死した
|
|
|
|
|
武田家の重臣・金丸筑前守虎義の五男、駿河の武将・土屋貞綱の養子となり土屋惣蔵昌恒と称した、三方ケ原の戦いで戦功をあげ武田勝頼の側近となる、長篠の戦いで養父・貞綱と兄・昌次を失い両土屋の家督を相続、織田信長の武田家征伐軍に勝頼が追い詰められたとき、狭い崖の道筋に立って左手に弦、右手に刀を持って敵軍の前に立ちはだかり、勝頼が自害する時間を作った、崖下の川は惣蔵に切られた武士たちの血で三日間も朱に染まり、三日血川(みっかちがわ)と呼ばれる、この片手千人斬りの伝説を打ち立てたのちに討死
|
|
|
|
|
筒井順国の子で筒井順慶とは従兄弟、筒井順慶の養子となる、山崎の合戦後に秀吉への人質となる、順慶の死後に家督を継ぎ大和郡山城主、四国征伐の功で伊賀・上野城主、その後九州・小田原の戦いに参加、朝鮮出兵は参加せず名護屋に留まる、関ケ原では東軍につくも城を落とされる、戦後は所領を安堵されるが家臣・中坊秀祐から素行の悪さの訴えられ改易、大坂の陣では大坂方内通を疑われ自刃
|
|
|
|
|
筒井定次の実父、筒井順慶の義兄にあたるといわれる、筒井家の重臣として筒井順慶を補佐した
|
|
|
|
|
筒井順興の子、筒井順慶の父、対立する越智氏等の国衆を押さえ台頭、家督を順慶に譲り隠居して比叡山に入る、しかし翌年没
、天然痘を患っていたといわれる
|
|
|
|
|
尾張・犬山城主成瀬家の家老、小兵衛一成、妻は成瀬正成の妹
|
|
|
|
|
織田信長の弟・信行の側近、信行の寵愛を受けて譜代の家臣と対立、二度目の謀反を画策した信行と共に誅殺された
|
|
|
|
|
豊後・大友宗麟の軍師、キリシタン信仰に批判的であった、宗麟が島津勢との対戦のため日向派兵を行うに際し、時期が適切でないとして延期を献言したが、宗麟はこれを拒否、石宗は秘伝の書を焼いて出陣し、討死した
|
|
|
|
|
長宗我部元親の三男、高岡郡の豪族・津野氏を継いだ、元親が豊臣秀吉に降ったとき、人質として秀吉のもとに送られる、藤堂高虎と親しかったので元親に疑われ、幽閉される、関ヶ原敗戦後に殺害された
|
|
|
|
|
尾張・松倉城主、加賀の豪族・富樫氏の庶流・前野氏の子孫、前野長康の父である説と勝定の娘が長康の妻であるとの説がある
|
|
|
|
|
坪内勝定の子、坪内利定の兄、通称・宗兵衛、織田信清の配下にあったが織田信長の勢力が増すと、木下藤吉郎を通してその配下に入った
|
|
|
|
|
坪内勝定の子、坪内為定の弟、通称・喜太郎、兄と共に豊臣秀吉に属したが衝突して放浪、徳川家康に召されて仕えた、関ヶ原では鉄砲隊を率いて活躍した功により羽栗・各務両郡六千五百三十余石を領す、子孫は幕府旗本として存続した
|
|
|
|
|
尾張・松倉の土豪、前野宗康の弟で坪内家の養子となり坪内家を継ぐ、信長に敗れた織田信安が坪内家を頼り寓居した
|
|
|
|
|
美濃土岐郡妻木村の小豪族、土岐氏の庶流で明智家の家臣、光秀の妻・煕子の父、本能寺の変では長浜城を守備するが、羽柴秀吉に攻められ降伏した
|
|
|
|
|
石田三成の家臣、関が原の戦いのときに大阪城にいた石田三成の子・重家を城外に連れ出し、京都の寺院にかくまった、重家の乳母の父といわれる
|
|
*印は著者の創作人物または実在したかどうかは不明な人
ページTOP
| HOME | | |