| |
| 頭文字この登場人物 |
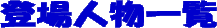 |
戦国本の登場人物の紹介 |
上総介の読んだ戦国本に登場する人物を紹介。主人公や脇役の紹介はこちら。
|
|
|
豊臣秀吉の叔父・小出秀政の子、母は秀吉の母・なかの妹・天瑞院、小出播磨守吉政、秀吉の馬廻り衆となり戦に従軍、播磨・龍野城主となり二万石を領した、のちに但馬で六万石を領するようになった、関が原の戦いでは父とともに西軍につき丹後・田辺城攻めに参加した、弟・小出秀家が東軍につき戦功をあげたため本領安堵、その後岸和田三万石に移った
|
|
|
|
|
名族・安曇部の後裔、安曇郡・小岩嶽城主、小笠原長時や村上義清が武田信玄に敗れたのちも中信濃で最後まで抵抗した、武田軍の猛攻に最後まで降伏せず自刃して果て、五百人の将兵ことごとく討死した
|
|
|
|
|
志摩・甲賀の地侍、伊勢北畠氏の配下にあった、甲斐を追われていた武田信虎を招き、その軍略で九鬼氏の波切を追放する、その後信虎に傾倒して武田姓をもらい、武田左馬助と称した
|
|
|
|
|
井伊家家臣、本姓は長野で上野・箕輪城主長野憲業の一族、長野業盛の子、長野業実、長野家が武田信玄に滅ぼされたのちに放浪し徳川家康に召抱えられた、その後井伊直政の家臣となる
|
|
|
|
|
神代宗元の子、少弐氏に仕えた、肥前・山内城主、少弐氏家中で台頭した龍造寺氏排斥に加わり、この後龍造寺隆信との抗争を続けた、龍造寺の重臣・小川筑後を討つなど互角に戦う、のちに隆信の挑戦状を受けて両軍が激突したが、神代軍中で謀反が起こり大敗した、大村領の波佐美に奔ったが、その後山内城に返り咲き再び抗争を始めた、のちに隆信と和睦し隠居、まもなく病死した
|
|
|
|
|
長宗我部国親の次男、長宗我部元親の弟、香宗我部家の養子となり家督を継いだ、安芸国虎との戦いで活躍し安芸城主となった、兄・元親の四国統一戦を陰から支え、最大の敵・三好氏を撃破する活躍をした、戸次川の戦いで島津氏に敗北、朝鮮の役に出陣する途中の長門国で病没した
|
|
|
|
|
播磨・上月城主、妻は黒田官兵衛の妻・幸園の姉、宇喜多直家に従う、官兵衛が織田家への随身を説いたが受け入れなかった、そのため羽柴秀吉軍に攻められる、籠城ののち開城を主張した家老に討たれた
|
|
|
|
|
伊予・湯月(道後)の領主、嗣子がなかった為、女婿・来島(村上)通康を養子とする、通康を当主にしようとすると一族の反対を受け、河野通存に家督を譲り隠居
|
|
|
|
|
来島城主、来島通康ともいう、河野通直の娘婿、父は村上顕忠で嫡男、河野通直の信頼が厚く後継者に押されるが、河野一族重臣の強い反対に遭って話は流れた、毛利元就配下で陶晴賢との厳島の戦いに参加し貢献した
|
|
|
|
|
徳川家の譜代の臣、三河・岡崎の三奉行のひとり、「仏の高力」と呼ばれた寛大な武将、徳川の関東移封後に武蔵・岩槻一万石
|
|
|
|
|
肥前・島原藩主、高力忠房の子、正室は永井尚政の娘、左近大夫、父の死去により島原藩主となる、政治に熱心ではなく藩の財政再建目的で島原の領民に苛税を強いたため、領民の訴えで島原藩は除封となった、のち仙台城に幽閉された
|
|
|
|
|
伊達家の臣、桑折貞長の子、出家して覚阿弥と称す、養子となった稙宗六男・四郎が早世したため、還俗して家督を継いだ、人取橋の戦いで活躍、郡山の役では軍奉行、摺上原の戦いにも出陣、隠居・剃髪して点了斎不曲と号した、子の政長が朝鮮出兵で病死したため、宗長の死後、石母田景頼が桑折家を継いだ
|
|
|
|
|
黒田家家臣、豊前入国後に五千石、小寺政職の家老の家であったが小寺氏没落後に黒田家に仕えた、朝鮮出兵で武功をあげ秀吉から一万石を賜る、恩賞を受けるために名護屋へ赴く途中に病のため対馬で死去
|
|
|
|
|
上野・箕輪城主長野家の家臣、武田家の上野侵攻によって箕輪城が落城したのち、内藤修理に仕えた
|
|
|
|
|
伊達家の臣、伊達晴宗の五男、幼名・彦九郎、国分盛氏の養子となる、千代城主、人取橋の戦いで活躍し、摺上原の戦い後は鮎貝城を守備、葛西・大崎一揆では米沢城留守居、蒲生氏郷の疑いを解くため名生城に人質として赴いたこともある、しかし政宗に疑われ殺害を図ったので佐竹氏のもとに逃亡、佐竹家臣として横手城に住む
|
|
|
|
|
大友義鎮の重臣、義鎮の廃嫡と塩市丸による家督相続に反対し誅殺された
|
|
|
|
|
上杉謙信の用心棒的存在、小島一忠、信玄がわざとけしかけた猛犬に腕を噛まれながらも顔色ひとつ変えずに主人の口上を述べた後、腕を一振りしてこの犬を叩き殺してしまったというエピソードがある猛将、「鬼小島」と呼ばれた
|
|
|
|
|
島津家の家臣、関ケ原の退却戦において東軍の真正面から伊勢路へ撤退することを主張、自らも捨て石となって戦死した
|
|
|
|
|
伊勢の北畠具教の弟で木造氏を継ぐ、兄に背き信長に通じる、その後は嫡男・具康に家督を譲り戸木城に移る、小牧長久手の戦いでは織田信雄に従う、しかし蒲生氏郷に戸木城を攻撃されて開城した
|
|
|
|
|
木造具政の嫡男、長政ともいう、父と共に織田信雄に仕えた、織田信長没落後は織田秀信の家老となる、関ヶ原では西軍に属した秀信に籠城を勧めたが通らず、野戦となると一隊を指揮して奮戦、その勇猛ぶりから戦後は福島正則に仕え、一万九千石を領した
|
|
|
|
|
佐々木六角家重臣、後藤但馬守賢豊、六角家嫡流に忠実であり再三定頼・義賢親子と敵対、義治の代になり謀反の汚名を被され惨殺された(観音寺騒動)
|
|
|
|
|
葛西家家臣・岩淵秀信の息子、幼名・又五郎、葛西家改易のとき九州に逃れキリシタンとなる、五島で洗礼したため姓を岩淵から五島に変えた、田中勝助の推挙で伊達政宗に仕え姓を後藤に変えるた、九州での異国との交流で鉄砲の名人となり、大坂の陣では鉄砲隊を指揮した、幕府のキリスト教禁止令が伊達藩にもおよび出奔、南部藩に逃げその地で死亡した
|
|
|
|
|
山内一豊の譜代の家臣、五藤三郎左衛門浄基の子、通称・吉兵衛、越前朝倉攻めでの退却戦で、一豊の顔に刺さった矢をわらじのまま土足で顔を踏みつけて引き抜いたといい、その「わらじ」は五藤家の家宝となった、本能寺の変後の伊勢・亀山城攻めにおいて討死した
|
|
|
|
|
山内一豊の家臣、五藤吉兵衛為浄の子、通称・市兵衛、内蔵助、一豊が土佐藩主になったときに五藤家は家老職となった
|
|
|
|
|
後藤又兵衛基次の嫡男、黒田長政の小姓、城井鎮房の謀殺のとき不覚をとって小姓を罷免、関ヶ原では黒田官兵衛に従って一軍を率い、大友家の豪将・吉弘嘉兵衛をはじめ兜首二十八を取った、しかし人妻との密通事件により領外追放された
|
|
|
|
|
別所家家臣、後藤又兵衛の父、後藤将監基国、三木城籠城中に別所長治を諌めたが入れられず、親しかった黒田官兵衛に子の又兵衛を預けて、落城時には主君に殉死した
|
|
|
|
|
後藤又兵衛基次の次男、後藤左門基則、黒田長政の小姓として福岡城に上がる、しかし能楽の催しで不意に小鼓の囃子(はやし)を命じられ屈辱のままやむなく囃子を務めた、その後無断で城を脱出し父・又兵衛のもとで自害を試みるが止められ、父と共に黒田家を出奔した、大坂の陣で真田軍とともに戦い討死した
|
|
|
|
|
小西隆佐の子、小西行長の弟、宇土城代、関ケ原のときは宇土城を守り加藤清正の侵攻をよく防いだ、その後開城し自刃する
|
|
|
|
|
前田家の家臣、進物奉行、大塩伝左衛門の娘婿、役儀怠慢・横領のかどで切腹を申し付けられた
|
|
|
|
|
天下一の鷹匠・小林家鷹の養子、徳川家康に仕え末裔は直参幕臣として明治維新に至った
|
|
|
|
|
甲斐・北巨摩郡を領する国人、武田信虎に仕え後に武田信玄の参謀となる、「高白斎記」を書いた駒井高白斎と思われてきたが、近年高白斎は政武の父・駒井昌頼であったとの説が有力
|
|
|
|
|
甲斐武田家の家臣、武田滅亡後に大久保長安に仕え佐渡金山の代官として派遣された
|
|
|
|
|
細川家の重臣、一色義俊誅殺時に弓木城で細川藤孝の娘・伊与を引き取る、その後弓木城の兵全て処刑した
|
|
|
|
|
米田求政の子、通称・助右衛門、父とともに細川幽斎に仕えた、姉川の戦い、小牧・長久手の戦いなどで功をたてる、関ケ原の戦いで岐阜城を攻撃中に戦死した
|
|
|
|
|
室町幕府に仕えた幕臣、足利義輝が殺されたとき医者として興福寺に潜入して覚慶(後の足利義昭)救出の手助けしたといわれる、その後は細川藤孝の家臣となる、剃髪して宗賢を称す、子孫は長岡姓を賜り肥後・熊本藩の家老職を代々務めた
|
|
|
|
|
立花家家老、薦野三河守、道雪に見込まれ優遇されて数々の手柄を立てる、道雪が立花家の名跡を継がせようと試みるが固辞、高橋紹運の長男・千熊丸を推挙した、立花宗茂が筑後・柳河城主となると城島城主四千石、朝鮮の役では渡海していない、関ヶ原では一人東軍につくことを主張したが宗茂に言を退けられる、戦後黒田家に召された
|
|
|
|
|
立花家家臣、薦野増時の父、河内守、立花鑑載が謀反を起こす際、鑑載によって舞楽の宴に招待され、立花山東城の井楼山で米多比大学とともに討たれた
|
|
|
|
|
伊達家の臣、小梁川親宗の子、高畠城主、中野宗時が相馬に出奔した際に高畠城下を通過させたことで輝宗の怒りを買う、最上氏の上山城を攻め、最上軍と戦った際は先鋒を務める、大内定綱との刈松田の戦いにも在陣、晩年は出家して泥蟠斎を称し、不断相伴衆として政宗に近侍、七十三歳で京にて死去
|
|
|
|
|
九鬼家の家臣、もとは金剛證寺の修行僧、九鬼嘉隆の片腕の武者頭として活躍、田城にて嘉隆の甥・澄隆を後見、澄隆没後は隠居し九鬼家の菩提寺仙遊寺の住職となった
|
|
|
|
|
江戸初期の幕府旗本、父は近藤季用、徳川頼宣に属し大阪冬の陣に参加、父季用に召還され金指近藤家を継いだ、明暦の大火では抜群の功績により幕府から賞される、文武を好み、旗本奴と町奴の暴挙を征したとされる、歌舞伎の幡随院長兵衛の芝居に出てくる近藤登之助としても知られ、旗本退屈男のモデルでもある
|
|
|
|
|
北条氏照の家臣、助実、出羽守、元・北条氏康の側近、のちに氏照印判状の奉者を勤めている、下野・榎本城主、奥州伊達氏との取次ぎを勤める、秀吉の来攻に備え狩野一庵・中山家範とともに武蔵・八王子城中の丸に籠城したが、落城の際に自害した
|
|
|
|
|
津軽為信の重臣、金信就の子、通称・小三郎、主水、関ヶ原の戦いのときに西軍派として堀越城に籠もった三将を討ち、その功により津軽姓を許された、為信の死後に三男・信枚と長男・信建の遺児・熊千代の後継者争い(津軽騒動)で熊千代側として争い、幕府の裁定で敗れ自刃した、信枚が密かに逃がし、新岡姓に改め開拓事業に生涯を費やしたともいわれる
|
|
*印は著者の創作人物または実在したかどうかは不明な人
ページTOP
| HOME | | |