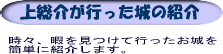 |
 |
||||||
 本丸跡 佐倉城は徳川家康が江戸幕府を開いた後の慶長十五年(1610年)に小見川から転封してきた譜代の土井利勝が、江戸の守りとして本格的な城郭の建設を命じた関東有数の壮大な規模を持つ平山城。
利勝は翌慶長十六年から六年間をかけて、千葉一族が手がけた旧鹿島城の縄張を東方台地にまで拡大し、元和三年(1617年)に完成した。築城にあたり家康は「天下の名城たらん」とその要害堅固さを称えたと伝えられる。 その後佐倉城は、代々譜代の大名が封じられ、老中職についた城主が徳川各藩中最多を数えたため、老中の城と言われたという。 明治維新後の明治六年(1873年)に、陸軍第一軍官第二連隊の営所建設のため佐倉城の建物は取り壊され、旧藩主は立ち退かされた。 |
|||||||
以下、国立歴史民俗博物館の内容 【 場 所 】 千葉県佐倉市城内町117 【開館時間】 3月〜9月: 9:30 〜 17:00 10月〜2月: 9:30 〜 16:30 【休 館 日】 毎週月曜日(ただし、祝日にあたるときは翌日) 年末年始(12月27日から1月4日まで) 【入 館 料】 【交通案内】 JR総武本線佐倉駅下車、ちばグリーンバス「国立博物館入口」下車 京成佐倉駅下車、徒歩約15分、またはバス約5分(「国立博物館入口」下車) 佐倉城地図  |
|||||||
 |
 |
||||||
|
追手門石碑 明治初期までは門があったようだが現在は石碑のみ。周りに中学校・高校がある。 |
土塁 佐倉城は石垣がないため、土塁を巧みに配置して城の守りとした。 |
||||||
 |
 |
||||||
|
姥が池 この池のそばで家老の娘をおもりしていた姥が誤って娘を池に落とし、困り果てて池に身を投げたと伝えられる。 |
門 城内にあった門が市内の酒造土井家に下賜されて表門として使われていたもの。後に市に寄付された復元したもの。 |
||||||
 |
 |
||||||
|
佐倉城の敷石 明治初期に陸軍の営所を置く際、佐倉城を取り壊し、その基礎を兵舎の基礎に転用したため敷石を埋め込んでいた。 |
空堀 城址には数々の空堀が残っていて、とても迫力がある。 |
||||||
 |
 |
||||||
|
二の門跡 本丸から大手門にいたる第二の門で「二の御門」と呼ばれていた門の跡。 |
正岡子規の碑 正岡子規が佐倉城に訪れたときに詠んだ詩「常磐木や 冬されなさる 城の跡」を刻んだ石碑。 |
||||||
|
|
|||||||