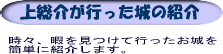 |
 & 豊田城 & 豊田城 |
 逆井城址 逆井城は北側に幅1km、南北30kmにわたる飯沼があり、別名・飯沼城といわれる。
戦国時代、この飯沼が小田原の後北条氏と佐竹氏・結城氏・多賀谷氏との境目だった。 天正五年(1557年)10月に玉縄城主・北条氏繁が飯沼城を築城。藤沢より大鋸引き職人ら呼び寄せて城を改修したという。城主となった氏繁は、佐竹・下妻方面の動向を本城に報告した。しかし翌天正六年に飯沼城中で没し、氏舜が城代となった。その後北条氏勝が城主となる。 天正十八年の豊臣秀吉による小田原征伐で後北条氏は滅亡し、飯沼城も廃城となった。 江戸時代の新田開発により、飯沼は湖水がなくなっている。 現在、逆井城は茨城県指定の史跡として主要部分が整備され、逆井城跡公園となっている。 |
|
【 場 所 】 茨城県坂東市逆井1234番地 【交通案内】 JR東北線古河駅から、16km 東武伊勢崎線東武動物公園駅から、19km 関東鉄道常総線石下駅から、15km  逆井城址公園地図 逆井城址公園地図 |
|
 |
 |
|
二層櫓 戦国末期の時代背景を元に、外観二層の容姿をもつ櫓として復元された。 |
関宿城門 関宿城門といわれるこの門は、本柱が門の中心線上から前方にずれている薬医門と呼ばれる。 |
 |
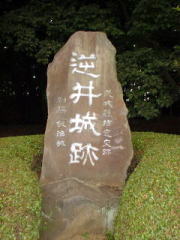 |
|
井楼矢倉 蒸篭と同じように井形に組んだ方形材を次々と組み上げた櫓。これが天守閣に発展したという。 |
逆井城址碑 公園の真ん中に立つ逆井城址碑。 |
 |
 |
|
主殿 本丸殿殿を模した主殿と枯山水の庭園があるらしいのだが、休館日だったので外からしか見れなかった。 |
観音堂 岩井市の大安寺にあったものを移築・復元したもので、天正十六年の建立時と弘化二年再興時の棟札が現存している。 |
 |
 |
|
鐘堀池 天文五年に逆井氏が北条氏に攻められ滅んだとき、城主の妻(または娘)が代々伝わる釣鐘をかぶって飛び込み自殺した池。 |
櫓門と橋 逆井城址の発掘調査を元に復元された。資料をもとに戦国時代末期の姿を想定している。 |
 |
 |
|
井楼矢倉から見た飯沼 戦国時代末期には東西役km南北約20kmの沼だったが、江戸時代に将軍吉宗の命により干拓された。 |
比高二重土塁 この公園には土塁が至るところに残っている。写真は比高二重土塁で堀の内側と外側に土塁があり外側に比べて内側が高くなっているのが特徴。後北条氏の築城の特色だ。 |
| 豊田城 | |
 豊田城(石下町地域交流センター) 逆井城址公園から15kmほどの石下町は平将門の子孫である豊田氏が治めていたが、天正三年に多賀谷氏によって滅ぼされた。
坂東武士団発祥の地・平将門の館や戦国時代に君臨した豊田氏の居館等にちなみ、石下町のシンボルとして石下町地域交流センターを建設したという。つまり歴史上の城跡とはぜんぜん関係ないらしい。 建物は五層七階で40mもあり、巨大な鉄筋模擬天守がそびえている。 |
|
 |
 |
|
豊田城址碑 実際の豊田城址(石下城)は、約2kmほどの河川敷にひっそりとたたずむ。 |
上善若水 石碑の横に立派な石碑がある。「じょうぜんはみずのごとし」と読むらしい。「老子」から句が書いてある看板があった。 |
|
|
|