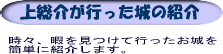 |
|
 国指定史跡「大内氏遺跡」館跡 龍福寺は毛利元就の嫡子・毛利隆元が、養父・大内義隆の菩提寺として、弘治三年(1557年)後奈良天皇の綸旨を受けて建立されました。
境内地は大内館の跡地で、南北朝時代の中頃の1360年、中国地方の豪族で守護職の大内氏二十四代・弘世が山口に移って以来大内氏の屋形があり、歴代大内氏はここで二百年間政務を執りました。京都に模した街づくりをして大いに栄えて、「西の京」と謳われています。天文十八年(1549年)に毛利元就も、次男・吉川元春、三男・小早川隆景をともなってこの館に参上し、大いに歓待されています。 この屋形は現在の龍福寺境内とほぼ一致する百間四方の敷地であったといわれ、学術的な解明を行うために昭和五十三年から発掘調査が行われています。 境内にある資料館は、大内氏と毛利氏の関係を知ることができる資料が多く保管されています。 また、大内氏は館北隣の築山にも居館を築き、「築山館」と呼ばれました。現在は八坂神社があり、弘世が京都から勧請した神社で「山口の祇園さま」と呼ばれ、「鷺の舞」が奉納されます。 |
|
【 場 所 】 山口市大字大殿大路119 【交通案内】 JR山口線山口駅車で約5分 大内氏館地図  山口市役所 経済部 観光課 |
|
 |
 |
|
龍福寺の門 この奥に本堂があるのだが、残念ながら修復工事のため見れなかった。 |
大内義隆卿供養塔 長門市湯本大寧寺にある大内義隆のお墓を複製したもの。 |
 |
 |
|
大内義隆辞世の歌碑 重臣陶隆房の謀反により自刃して果てる前に詠んだ辞世が刻まれています。 |
義隆木像 龍福寺資料館の前にある木像。 |
 |
 |
|
築山館跡 連歌師・宗祇もその壮大さを歌に詠んでいるほどのものだった。 |
八坂神社 町屋づくりの建物が建ち並ぶ竪小路の傍らに建つ、朱色の大鳥居が印象的な神社。 |
|
|
|