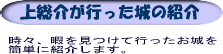 |
 (厩橋城) (厩橋城) |
 前橋城跡の碑 入口 もともと厩橋城と呼ばれていた前橋城は、上州・箕輪城の支城として長野方業によって室町時代の中期に築城された石倉城がその前身です。長尾賢忠が城主のときに利根川の洪水で崩壊したため、残った三の丸に築城し直しましています。
天文二十年(1551年)、関東管領・上杉憲政が北条氏に敗れて越後・長尾景虎(のちの上杉謙信)のもとに落ちため、厩橋城は北条軍に包囲され、賢忠は降伏し城を明け渡します。 永禄三年(1560年)長尾景虎の上野国進軍により、厩橋城は北条氏から奪回され、再び賢忠が城代となりました。その後もたびたび越後勢と北条・武田との間で城をめぐる争いが絶えませんでしたが、永禄十一年(1568年)、上杉謙信と北条氏康の和睦がなって、両者がこの城で会見しました。そのとき城代として、上杉家の北条(きたじょう)高広が入っています。 謙信が没すると、上州に進出した武田勝頼に攻められ、北条高広は降伏して城は武田氏のものとなりますが、高広はそのまま城代として残りました。 天正十年(1582年)に織田信長によって武田氏が亡ぼされると、上州は滝川一益に与えられ厩橋城に入ります。しかし本能寺の変によって一益は上野を撤退し、北条氏と神流川で戦って敗れ、厩橋城は再び北条氏の城となりました。 天正十八年(1590年)、豊臣秀吉の北条攻めのとき、浅野長政が厩橋城を攻め落とします。その後、徳川家康の関東移封によって、家臣の平岩親吉が三万三千石で入城しました。慶長六年(1601年)には酒井重忠が三万三千石で入城し、城の大改修を行って近世城郭へと変貌させました。慶安二年(1649年)、酒井忠挙によって「厩橋」は「前橋」に改称しされます。 寛延二年(1749年)、松平朝矩が十五万石で入城し、以降、明治維新まで越前松平家の居城となっています。明和四年(1767年)本丸が利根川の浸食により崩壊の危機に曝されたため、松平氏は居城を武蔵・川越城に移し、前橋領には陣屋が置かれて、明和六年(1769年)に前橋城は廃城、破却されました。 天保年間の利根川の改修工事により、城の崩壊の危険が減少したたため、藩主・松平直克は文久三年(1863年)に前橋城の再築を開始し、慶応三年(1867年)に竣工し直克が入城しました。しかし、僅か半年後に大政奉還が行われ江戸幕府は終焉します。 明治四年(1871年)の廃藩置県によって、前橋城は僅か6年で廃城となりました。本丸御殿は群馬県庁として利用されましたが、平成十一年(1999年)に建て替えられ、地上33階・地下4階の超近代ビルに生まれ変わっています。現在の城跡にはその面影はほとんどなく市街化しています。 |
|
【 場 所 】 前橋市大手町1丁目1−1 【交通案内】 JR両毛線前橋駅下車、バス約6分 新前橋駅下車、バス約7分 前橋城地図  群馬県庁ホームページ |
|
 |
 |
|
土塁 群馬県警本部の横にある土塁。 |
土塁の上 歩けるようになっているが、保存上、立ち入り禁止となっていた。 |
 |
 |
|
前橋城跡の碑 くの字形になっている土塁の角に建っているが、案内板は風化して文字が読めない状態。 |
高浜門の土塁 県警本部の裏側にある土塁。高浜門があった場所あたりと思われる。 |
 |
|
|
前橋城復元図 県警本部の横にある復元図。前橋城跡探索コースの記載もある。 |
|
|
|
|