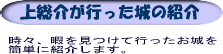 |
 (懐古園) (懐古園) |
|||||||||
 小諸城址懐古園 小諸城の起源は、木曽義仲の武将・小室太郎光兼が築いた館に始まる。その後小室氏は衰退し、南北朝時代に北朝方の大井氏が小諸佐久地域を支配した。
戦国時代に入り、村上氏の攻撃によって岩村田の大井宗家が滅亡したため、長享元年(1487)、大井光忠は要害の地である中沢川のほとりに小諸城の前身・鍋蓋城を築城した。さらにその子・光安が出城として乙女城(別名・白鶴城)を現在の二の丸付近に築城した。 天文二十三年(1554)、甲斐の武田信玄の侵攻で鍋蓋城以下の諸城は落ち、以後約三十年間、武田氏の城代によって支配される。信玄は重臣・山本勘助と馬場信房に命じて鍋蓋・乙女城を取り込んだ新たな縄張りをして城郭を整備し、大城郭としたのが小諸城の原型である。 天正十年(1582)武田氏滅亡後、小諸城は織田信長の領国となり滝川一益の持城となるが、本能寺の変が起きると北条氏と徳川氏の争奪が展開された結果、徳川家康の領有となり依田信蕃が城代となった。信蕃死後は子の松平(依田)康国に与えられた。 豊臣秀吉が天下統一を果たすと、天正十八年(1590)に仙石秀久が五万石で封ぜられる。秀久が城の大改修と城下町の整備を行い、今日の遺構の残る堅固な城を完成させた。 江戸時代になり、元和八年(1622)秀久の子・忠政のときに仙石氏が上田に移り、小諸城は徳川家光の弟・忠長の領有するところとなり、城代が置かれた。 寛永元年(1624)に松平憲良が入り、その後青山宗俊、酒井忠能、西尾忠成、石川乗政、石川乗紀と城主が変わり、歴代藩主は徳川譜代がつとめた。 元禄十五年(1702)越後与板藩から牧野康重が一万五千石で入封後は版籍奉還まで約170年間、牧野氏が十代にわたって居城とした。 明治四年(1871)の廃藩置県後、城域は払い下げられ、小諸藩の旧士族の手により本丸跡に神社が祀られ、懐古園と名付けられた。 |
||||||||||
【 場 所 】 長野県小諸市丁311 【開館時間】 8:30〜17:00(入場は16:30まで) 【休 館 日】 3月中旬〜11月末まで無休開園/12月〜3月中旬まで毎週水曜日 年末年始(12月29日〜1月3日) 【入 館 料】 ・共通券 (懐古園内散策・藤村記念館・徴古館・郷土博物館・小山敬三美術館・動物園) ・散策券(懐古園内散策・動物園)
【交通案内】 しなの鉄道又はJR小海線、小諸駅下車、徒歩10分 小諸城地図  小諸城址懐古園ホームページ |
||||||||||
 |
 |
|||||||||
|
三の門 明和年間に再建された二層寄棟造瓦葺の楼門で、国指定重要文化財。 |
本丸・天守台 かつては三層の天守閣がそびえていたという天守台。野面積みが往時の面影を残す。落雷によって焼失したと伝えられる。 |
|||||||||
 |
 |
|||||||||
|
二の丸 乙女城が設けられた場所で、仙石秀久のときには屋形が構えられていた。関が原のときには南下した徳川秀忠の宿所にあてられた。 |
黒門跡 小諸城一の門で本丸御殿の入口にあった黒塗りの門跡。仙石秀久が建てたもので、現在は小諸市八満の正眼院にある。 |
|||||||||
 |
 |
|||||||||
|
黒門橋 算盤のように多数の車輪が橋の下に付いていたことから別名・算盤橋という。 |
馬場跡 往復するだけの鉄砲馬場といわれ、現在は桜の名所として有名。 |
|||||||||
 |
 |
|||||||||
|
懐古神社 本丸跡に祀られた懐古神社。 |
鏡石 小諸城築城のときに山本勘助が研磨し、この石に向かって朝夕清鑑したと伝えられる。 |
|||||||||
|
|
||||||||||