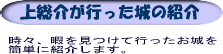 |
|
||||||
 古河城本丸跡の碑 古河城(古河公方館)は、源頼朝の御家人・下河辺行平が館を構えたことに始まります。永徳二年(1382)に下河辺朝行が小山氏に滅ばされ、その後、関東管領(鎌倉公方)足利持氏の領地となります。
嘉吉元年(1441)の結城合戦では、古河城に野口氏行らが籠もり、上杉清方らの大軍に包囲されたのちに落城します。戦後に許された持氏の三男・永寿丸(成氏)が宝徳元年(1449)に関東管領となり、康正元年(1455)に古河に移って城館を築いて古河公方と称しました。四代・足利晴氏は北条氏康の庇護の下に存続しましたが、天正十一年(1583)に五代・足利義氏が跡継ぎ亡く没したため、古河公方足利氏は断絶します。 天正十八年(1590)の豊臣秀吉の小田原攻めののちに徳川家康が関東に入封すると、小笠原秀政が古河城主となります。その後、慶長六年(1601)に松平康長が二万石で入封して、渡良瀬川に面する広大な近世城郭として古河城を築城しました。奥平氏、永井氏を経て寛永十年(1633)に土井利勝が八万石で入封し、本丸に天守の代わりの三層櫓を築くなど古河城を大修築し、城下町も整備しました。 その後、堀田氏、松平氏、本多氏など城主となり、宝暦十二年(1762)に土井氏が返り咲いてから、明治維新まで藩主となっています。 現在、本丸跡は水害防止のための河川改修で川の底となっていますが、城跡の一部である出城を利用して古河歴史博物館が建っています。 |
|||||||
古河歴史博物館 【 場 所 】 茨城県古河市中央町3丁目10番56号 【開館時間】 9:00〜17:00(入館は16:30まで) 【休 館 日】 月曜日・国民の祝日の翌日・館内整理日(原則として毎月第4金曜日)・年末年始 【入館料金】
※このほか、歴史博物館・文学館・篆刻美術館の3館共通券あり 【交通案内】 JR宇都宮線古河駅から徒歩15分 東武日光線新古河駅から西城まで徒歩25分 古河城地図  古河歴史博物館公式ホームページ |
|||||||
 |
 |
||||||
|
出城諏訪郭跡の碑 現在、古河歴史博物館が建っている場所がその場所です。 |
乾門 数少ない遺構のひとつである福法寺山門。古河城取り壊しのときに檀家が払い下げを受けて寺に寄進したもの。 |
||||||
 |
 |
||||||
|
鷹見泉石記念館 博物館の前には、古河藩家老・鷹見泉石が隠居後にもっぱら蘭学にいそしんだ屋敷がある。 |
土井利勝の像 土井利勝が建立した「正定寺」にある像。ここには土井家の墓所がある。 |
||||||
| 2007.2.22撮影 | |||||||
 |
 |
||||||
|
古河公方館跡碑 古河総合公園内にある古河公方の館跡碑。 |
空掘と土塁跡 まわりには、古い民家が移築されています。 |
||||||
| 2007.3.21撮影 | |||||||
|
|
|||||||